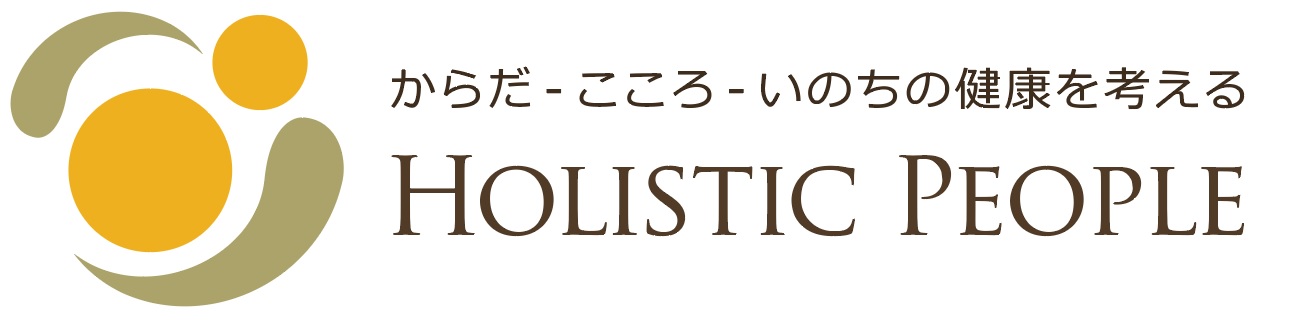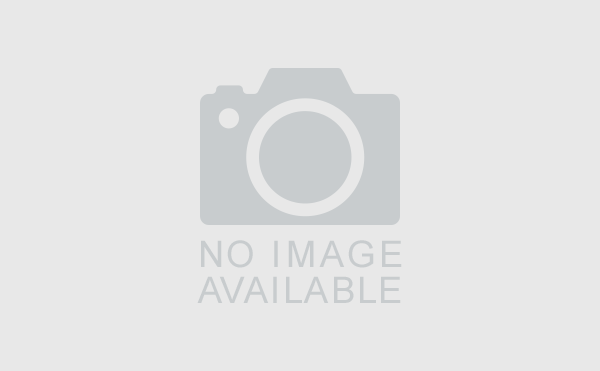園芸療法~植物的な時間の中で癒される
『HOLISTIC MAGAZINE 2005』より
園芸療法
~植物的な時間の中で癒される~
<取材>園芸療法家・グロッセ世津子さんに聞く
植物の恵みを活用する園芸療法。園芸療法への理解が日本でまだ乏しかった頃から、園芸療法に取り組んできた、園芸療法実践家のグロッセ世津子さんをお訪ねしました。
園芸療法ではどのように人を癒していくのか、またその際に植物がいかに寄与するのかなど、園芸療法についてうかがいました。
(本インタビューは「HOLISTIC MAGAZINE 2005」に掲載されたものを再掲しています。写真はイメージ画像で、実際のものとは異なります。)
…………………………………………….
園芸療法の3つの要素
園芸療法を考えるとき、園芸を媒介することで3つの要素があります。
1つは、植物を育てるという行為です。どのステージ、どの成長の過程から植物を利用していくかは、その状況で考えていけばいいと思うのですが、種を育てるパワーというのはものすごい。できればやはり種から育てるということを1回でも2回でも入れて欲しいと思います。育てる、そしてケアする、収穫する、利用する。この一連のプロセスがあります。
2つ目の要素は、収穫物で何をするかということです。収穫物も多面的に利用できます。調理をしてもいいし、販売してもいいし、人に分けてあげてもいい。アート活動に使ってもいいし、クラフト、何か工作物みたいなものを作ってもいい。
3つ目の要素は、植物のある環境です。それが庭であったり、植物がいっぱい置いてあるところだったりする。この3つの要素があるわけです。
植物の恵みはいつもある
育てるというなかには大きく分けて、知的効用であるとか、精神的効用、情緒的効用、社会的効用、身体的効用といったような効用が得られます。
例えば身体的なことでは、種を蒔くという1つの作業を取り出して、さらに細かな工程に分解できるとします。これら全部の工程をひとりでやらなくても、今やってもらうことを見つけることができるのです。
それはポットを押さえてもらうことかもしれないし、土を砕いてもらうことかもしれない、種の袋を持ってきてもらうことかもしれません。とにかく、そういう大きな流れのどこかに、その人のやれることを見つけることができる。そしていろいろな工程でその人の関われることを見つけ出してあげて、やっていくうちに結果として花になる。
精神的なことや感情的なことにしても、自分のケアに応えてくれるという成果が花だったり、野菜だったり、目に見える結果として現れてくれる。それを手放しに喜べるわけです。そして第三者もすごく反応しやすいのです。
また、患者さんのなかには「病気が治らないと元の生活に戻れない」「損なわれた機能が回復しないと元の自分にはなれない」と思い込んでいる人がいます。治るまでその人は「それでも私はここにいてもいいんじゃないか」「生きててもいいんじゃないか」という実感がなかなか持ちにくい。そのなかで、治らなくても、よくならなくても、命を育てるというダイナミズムに参画できる。それを周りの人と共有できるということで「もしかしたら、私はここにいてもいいのかな」「やっぱり生きてみようかな」といった気持ちになれるのです。
そして、育てられない、体が動かない時にも、自然の恵みはあるのです。もし私が寝たきりでも、植物が季節を運んできてくれる。蝶々を運んできてくれる。そして風が吹いているって感じさせてくれる。雨が降れば葉に雨のあたる音が聞くことができる。
これは病気だから、病気じゃないからというわけではなく、あるものを享受できるのです。それが恵み、プレゼント、ギフトです。
多くの方と関わってきて感じたのですが、特に絶望された方に「がんばろうよ」というのはとても空しい。約束できない治癒なり回復というのは伝えにくい。でもその時に「何かできることが絶対にある。楽しむことができるんですよ。どんな状態にあってもワンダフルだよ、この世界は」ということを早く伝えてあげると、その人のなかに生きたいという欲が出てくるのです。
だから、痛くてもつらくても一段上がれると思える人はいいけれども、本当にリハビリの出口が見えてない人にそういうことは、しんどい。リハビリをしながらそのプロセスを楽しめたら、もう出口も忘れるくらい楽しんでもらう。それを早い段階で伝えることができると、本当にその人が変わることがあるのです。
人の計らいを超えて
植物を育てるということは、思い通りにいかないという部分がとても大きいものです。私たちが計画通りに効率を求めようとすると無理が出てきますからね。すると「消費する園芸はどういう風にする?」「大量生産をしよう」とか、「確率的な成果表を出そう」とか、「もっと作るために人工培養でやろう」とか、そんな風になってきますよね。でも1つ1つの花の個性は、そこではもう考えられなくなってきます。
計画通りにいかないということは、私の計らいを超えているということです。すると待たなければいけないのです。その時期が来なければ、事は起こらないということに気づくのです。
それから、生命あるものはなくなる。枯れてしまいます。しかし終わりかと思ったら、土に還っていく。あるいはこぼれ種として翌年またそこから発芽する。その世代の種はもう花になり終わったかもしれないけれど、次世代を残していく。私たちの目に見えない世界で生命はちゃんとサイクルに従って営み続けているわけです。
目に見えることばかりで、私たちは物を考えようとしているし、理解しようとしているし、評価されてしまうのですが、目に見えないところにも、ちゃんと生命が生きているという実感が持てるようになるのです。
すると見えない世界に目を向けてみる気持ちが出てくる。この人は自閉症だ、この人は統合失調、これらは目に見えることです。でも目に見えない世界で、その人はどのように感じているのか。何を、その人は声として持っているのか。これは私たちの計り知れないところです。
だけどそこに耳を澄ませていたい。植物を育てていると、そんな気持ちになれるのです。
植物的な時間と動物的な時間
もうひとつの気づき、それは植物的な時間と動物的な時間です。
動物的時間は「する」という時間だと思います。いかにアクティブであるか。私たちは、「する」ということで評価されているわけです。生まれたときからそういう社会の中に置かれている。
そこでは「できない」ことはマイナスです。そうやって駆り立てられて生きている。障害や病気というのは、「する」という動物的な時間枠のなかで考えるとマイナスなわけです。
「する」ことができないことが多かったりすると。その中で評価されて疲れてきて、あるいは病気とか障害というマイナスイメージを自分で持ってしまう。
「する」ということで自分を見た場合、世間が見る目がありますね。そして自分で自分を見る目、これは深い。病気になった方やお年を召した方は、前はできていたのにできなくなる。そして病気になる、障害を持っていることに絶望する。自分のなかで自分を評価してしまう。
植物的な時間は、植物は、あなたの計らいに頓着せず、与えられた条件の中で生きれば枯れ、サイクルがくれば何らかの形で復活する。生命のサイクルを、個という形ではなく、次世代につないでいく。それは「ある」という時間なのです。
その「ある」という時間に身を置いたとき、「なにができない」ということで自分を評価していたけれども、「まあ自分は自分でいいかな」と何となく思える。そういう時間の概念を教えてくれるのです。
それをどうやってセラピーに使っていくか。それは、「してもらう」より、「まず、いてもらう」。能動的な作業をしてもらうことがいいかどうかを、みなくてはならないわけです。
植物は、黙っていても生えてくる。そして、そこにあり続ける。自分があること、生命そのものがあるということになぐさめられるのです。
レッテルの向こうに
例えば痴呆の方が、ものすごいレッテルで見られる。問題行動あるから大変。徘徊して意味もなく暴力を振るう。でもそれには本当は意味がある。そういう風に思われていることで、どれだけの人たちが傷ついているか。痴呆のAさんではなく、80年、90年、100年もの歴史をもっている、例えば「グロッセ世津子」という物語があるのです。
レッテルはそれぞれの立場で、貼る、貼られるものです。だから便宜上、必要な場合もあるわけです。だけどそのレッテルだけを見ないことです。それは一部でしかありません。
こんな感性や表現方法を持っていたとか、こんなに優しい気持ちを持っていたとか、こんなにがんばり屋さんだったのかとか、園芸療法を通してその人のいろんな側面が見えてくるのです。
例えば障害とか病気がその人の大半を占めているような場合でも、その人はそれだけで成り立っているのではないのですから、今まで光が当たらなかった部分のものを、表現してもらう媒体として、園芸療法は優れていると思うのです
私が園芸療法が本当にいいなと思うところは、セラピストは、きれいな格好して後ろに手を組んで見ているわけじゃなくて、一緒にやるのです。だから「暑いよね。でもあと5分がんばろうね」「これ終わったら水飲みたいね」とか、とにかく共感できる場面があるのです。
すると、一方的に権威のある専門家に囲まれた生活を強いられている人々にとって、喜びも含めて共感しましょうというのではなくて、つい熱中てしまう。だから喜怒哀楽を出してしまうわけですよ。そしてとにかく楽しいと思う。「私の隣にいるこの人、こんなに楽しそうにしている」と感じて、それが「私といることが楽しい」ということにもつながっていくような気がするのです。
生命と生命の出会いに託す
1粒のちっちゃな種があります、その小さな世界には、全部の情報が入っていて、その情報が開花するだけなのです。その情報の開花に、必要な条件を整えてあげるのが園芸ということです。
それがわかったときに、私のセラピーもそうだということがわかったのです。それぞれの人が持っている情報、生まれもってきた、人生を咲かせる情報をみんなが持っているのです。
そうした情報について、どうやったら咲くのか、咲かせることができるのか、そのための環境設定を、ああでもない、こうでもない、これはどうか、あれはどうかと、植物を使って提案するのが私の療法なのです。
療法というと、治療計画があって、まずは目標を立てるものじゃないですか。この目標通りということ。これはいいのです。
でも園芸療法をやっていると、計画しなかったことが、どんどん起きてくるわけです。そんなことを見てくるとホリスティックだなと思います。
こういう1つの治療目標を立てたのにもかかわらず、こんなこともできるようになった、その方の潜在能力が引き出されたとか、こんな素晴らしい面が引き出されたとか、こんな物語が引き出されたとか、なんか、いっぱい出てくるのですね。
だから、生命自身が私の計らいを超えている。だから、あんまり私は計らうということをしないで、託すのです。生命と生命の出会いに託す。そして、私もそこに実は託されるのです。
取材・文:今田信也
(HOLISTIC MAGAZINE2005-2006より)
グロッセ 世津子さん 園芸療法実践家・みどりのゆび代表
北海道生まれ。立教大学仏文科卒業後、フランスのブザンソン大学へ留学。ベルギーに13年暮らし1987年に帰国。日本における園芸療法の普及を目指し、全国各地での実践や講演、執筆活動を行われていた。
主な著書
『園芸療法のこころ』(ぶどう社)
『自然が正しい』モーリス・メセゲ(著) グロッセ世津子(訳)(地湧社)
『園芸療法新装版』(日本地域社会研究所)
© NPO法人日本ホリスティック医学協会 All Rights Reserved.
本サイト記事・画像の無断転載・無断使用を禁じます。