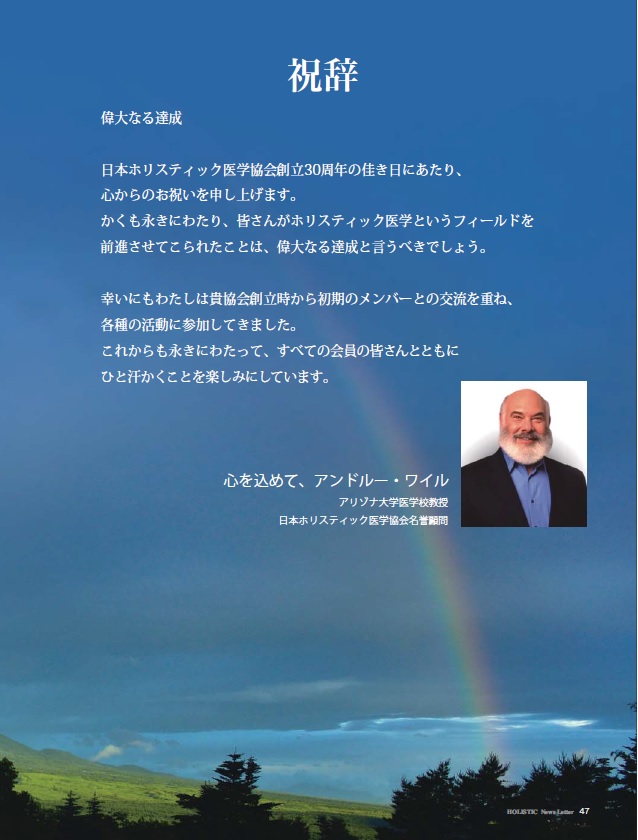ホリスティック 30年の雑感(上野圭一)
『HOLISTIC MAGAZINE 2017』
ホリスティック 30年の雑感
上野 圭一(翻訳家・NPO法人日本ホリスティック医学協会名誉顧問)
日本ホリスティック医学協会が誕生したのは、先行の同種組織がアメリカ、イギリスなどに生まれてから7、8年後のことで、いわゆる先進諸国が「ホリスティック」という概念に注目しはじめた時期に相当する。
とりわけ医療や教育など、専門分化が進みすぎてその分野の全体像が見えにくくなったことからくるさまざまな齟齬を解決するための思考法として注目されていたのだ。
日本の協会も欧米の協会も、したがって思想的には共通の基盤のうえに立っていたと思われるが、その協会設立のプロセスがやや異なっていた。
欧米のそれが医師やオステオパシー医など、プロの治療家たちが集まって設立したのにたいして、日本のそれがまだプロにはなっていない医学生有志たちの努力によって設立されたところに特色がある。
医学を学んではきたが医療の提供者にはなっていない、いわば医療の利用者である市民のひとりとして、現在学んでいる医学に少なからぬ疑問を抱き、オルタナティブを模索していたこころある学生たちが、アンドルー・ワイルの思想にそのオルタナティブの可能性を見いだし、ワイルの著書『人はなぜ治るのか』の読書会をはじめたところから、日本の協会の歴史ははじまったのだった。
そのささやかな読書会のスーパーバイザーとして東京医科大学の衛生学教授・藤波襄二先生がおられたこと、それがまことに幸いだった。衛生学という、臨床医学よりも大きな視野に立って人間と社会の健康を見わたすことのできる学問を身につけておられた藤波先生は、いち早くワイル思想に深く共鳴され、学生たちの読書会に一切口を出すことなく、静かに見守っているという態度を貫かれた。
信頼感で結ばれたその師弟の関係が、のちに設立されることになる協会の基調トーンになり、ボランティアという無償の活動を30年も持続させ、発展させていった原動力なったのはまことに尊いことだと思う。
カタカナ表記の理由
権威あるリーダーの音頭取りもなく学生主導で自然発生的に生まれた協会は、設立からしばらくのあいだ、理事会で「ホリスティック」というカタカナことばを使うことの当否をめぐって長い議論がつづいた。「全体論的医学」「全体医学」「包括的医学」「まるごと医学」など、なんとか日本語にしようと努力したが、結局は適切な訳語が見つからずにカタカナで行くことになった。
医学生たちの読書会でテキストに使われた『人はなぜ治るのか』の翻訳者として、ぼく自身もそのカタカナことばには悩まされていた。「全体論」という哲学用語が、日本では「全体主義」と混同されるのではないかという危惧がつきまとっていたからだ。
『人はなぜ』の前年、1983年された『現代アメリカ健康学』(アーヴィング・オイル著、日本教文社)では「ホリスティックヘルス」ということばにたいして「全体観的健康観」に「ホリスティック」のルビを振るという苦しい訳語を当てている。それがおそらく、日本の書籍で「ホリスティック」ということばがはじめて紹介されたケースになったのではないかと思われるが、いま読み返すと汗顔のいたりである。
カタカナ表記についてのわだかまりは長くつづき、80年代末にはある小冊子に「『ホリスティック』が消える日」というエッセイを書いている。
「ヘルス」にはもともと「ホリスティック」という意味が隠れているといいたかったのだ。少し長くなるが、その一部をかいつまんで引用させていただく。
『ホリスティックヘルス』は1970年代から欧米で盛んに使われるようになったことばですが、じつはトートロジー、つまり同義反復語(語源に遡って直訳すれば、このことばは『全体的全体』とも訳せる)であり、ことばに敏感な人の耳にはやや饒舌に響く表現、いわずもがなといった印象を与える表現なのです。
トートロジーが一部の人にそれと意識されながら人口に膾炙されていくとき、その伝播流布の原動力になっていることばそのものに、ある種の呪術性が働いている、言霊の力が発揮されていると考えなければなりません。
あるいは逆に、多少耳に不快に響いても、当座はそのことばを必要としている人たちがひじょうにたくさんいると考えなくてはなりません。『ひろく世に知られ、いわれること』を意味する『膾炙』とは『美味』な料理(『膾』はなます、『炙』はあぶり肉)の代表であり、美味だからこそ自然に広範囲の人々に伝播されていくわけですが、美味でもないものがたとえ耳にやや不快で口に多少苦いものであっても伝播していくのは、人々になんらかの薬効がありそうだと感じさせるものがそこにあるからにほかなりません。(『クスリ』とは『奇すしいもの』であり、必ず呪術性を伴っています)。
『全体』とはかつて、ことばにできないもの、ことば以前のものでした。あえてことばにするなら、それは『一』つまり『ひとつ』のことでした。
バクテリアも動植物も地球も、すべてが有機的にひとつにつながり、互いが互いを必要としながら生成流転をくり返していく壮大なひとつの宇宙ドラマ。
そのドラマにことばという鋭利な刃物をもった人間が参加し、ひとつだった宇宙を切り裂いた瞬間から『部分』が生まれ、同時に『全体』という概念が生まれます。『光』と命名した瞬間に『影』が生まれ、『一』は『二』になるのです。『ホリスティックヘルス』ということばは、そのことを思い出すための、多少苦いクスリです。『ヘルス』が『忘れていた全体性を回復した状態』である以上、そのことを思い出し、全体性を回復して真の『ヘルス』に到達した日、『ホリスティック』という冠は消える運命にあるのです。
その日の到来が一日も早からんことを!
呪術としてのカタカナ
そもそもカタカナは奈良時代に僧侶が中国語の教典を読み書きする補助として発明されたもので、「意味」ではなく「音」を写すために使われてきた。しかし、ときには単なる音のみならず、呪術的な意味を宿すことがあり、天皇の宣命をはじめ、神の声、神々しい判決文など、神秘的、超越的な声を表現するときには昔から漢字やひらがなではなく、カタカナが使われてきた。
社会学者の大澤真幸さんは、日本人の感覚のもっともプリミティブな層を率直に表現する文字がカタカナだといっている(『げんきな日本論』橋爪大三郎さんと共著、講談社現代新書)。
カタカナで表現されることばに微妙にオーラを感じるのが日本人で、「それは日本人のかなりベーシックでプリミティブな経験や感受性と対応している」と大澤さんはいうのである。
どうやら「オーラ」「ベーシック」「プリミティブ」と連発されると、なんとなくそこに呪術性や超越性を感じてしまうのが日本人らしい。
日本びいきの外国人で、日本を愛するあまりからか、日本語におけるカタカナ表現について憤慨する人がいる。「欧米語をカタカナで表現しても、発音はぜんぜん違うし、意味がない。欧米に追随せずに、堂々と漢字やひらがなで表現すべきだ」という人たちだ。
日本をそれほどにまで思ってくれるのはありがたいが、カタカナは欧米追随のしるしではなく、長い歴史をもつ日本語の大切な記号のひとつなのだと教えてあげてほしい。
創立30年の現在、欧米では統合医療組織と融合して、ホリスティック医学協会が衰退しているのにたいして、日本ではじわじわと成長しているのは、もしかしたら呪術的なカタカナ効果なのかもしれない(笑)。
ワイル仕込みの統合医療を肌身で知ろう
アンドルー・ワイルは、アリゾナ大学統合医療プログラムに全世界から集まってくる意欲的な若手医師たちに、こう教えているそうだ。
「きみたちがアリゾナで学んだ統合医療はアリゾナ版のモデルでしかない。ここで学んだことを故国にもち帰り、きみたちがそれぞれ選んだ地域で仕事をはじめるとき、いちばん大切なのはその地域の風土・歴史・信仰・住民のメンタリティ・産物など、その地域に特有の利点や美点を最大限に活かした方法で医療を実践することだ。その方法を発見し、考案することも統合医療の重要な使命なのだ」
アリゾナで統合医療を学んだ日本人医師たちは、みごとなまでにワイルの教えをまもり、日本の各地に散らばって、それぞれ一見はまったく異なる医療を実践している。画一性はほとんど見られない。第1期生の山本竜隆さんがはじめた「富士山静養園」ひとつを見ただけでも、そのことは瞬時にわかるはずだ。
共通しているのは「治療より治癒」「検査データよりライフスタイル」「個別性より関係性」などを重視する、ワイル仕込みのクライアントへのまなざしである。
その統合医療を、帯津良一先生は「ホリスティック医学に到達するための橋頭堡だ」と喝破されている。橋頭堡とは「相手を攻めるための足がかり、よりどころ」のことで、上陸作戦で使われる軍事用語だ。
上陸直後にまず占領し、後続部隊の上陸を援護したり、その後の攻撃のための足場とする陣地をいうわけだが、帯津先生は「ホリスティック医学への道は迂遠であり、まず足場が必要だ。その足場が統合医療なのだ」と見ておられるのだろう。
だとすれば、ホリスティック医学という迂遠な相手(目的地)に到達するには、いま日本の各地で実験的に行なわれているワイルチルドレン(アリゾナで統合医療を学んだ日本人医師たち)の診療現場を積極的に見学し、「足場」とはなにかをそこから学ぶ必要があるのではないか。
ホリスティック医学協会はすでにワイルチルドレンたちと親しく、個人的な交流をもっている人も少なくないと思うが、協会として彼らの活動の全体像を把握し、理解を深めることは互いの前進につながるのではないかという気がする。
わがホリスティックライフ
伊豆の伊東に移住してから10数年がたつ。いつのまにか後期高齢者の烙印を捺される身となり、東京にはますます足が向かなくなった。
毎日、市民が「三大名湯」に選ぶ温泉のひとつ、「緑風園」の湯に浸かるのが習慣となり、温泉仲間もふえた。東京の銭湯より安く利用できるその温泉に、宿泊客がくる時間前に集うのは老人ばかり。80代、90代の町民たちと四方山話をしていると世俗の欲も薄れ、ただ地球マグマの恩恵に身をゆだねるだけで平安な心境になってくる。
これもまたホリスティックライフのひとつなのかなと感じる日々である。
(HOLISTIC MAGAZINE 2017より)
上野 圭一 うえの・けいいち
1941年生まれ。早稲田大学英文科、東京医療専門学校卒。翻訳家/鍼灸師/日本ホリスティック医学協会名誉顧問
世界の代替療法、ホリスティック医学を先駆的に研究し、多くの書物の翻訳を手がける。
<著書>
『代替医療 オルタナティブ・メディスンの可能性』角川文庫(2002)
『補完代替医療入門』岩波新書 (2003)
『わたしが治る12の力 自然治癒力を主治医にする』 学陽書房(2005)
<訳書>
『人はなぜ治るのか』アンドルー・ワイル/日本教文社(1984)
『太陽と月の結婚 意識の統合を求めて』アンドルー・ワイル/日本教文社(1986)
『ナチュラル・メディスン』アンドルー・ワイル/春秋社(1990)
『魂の再発見 聖なる科学をめざして』ラリー・ドッシー 井上哲彰共訳/春秋社(1992)
『癒す心、治る力』 アンドルー・ワイル/角川書店(1995)
『いのちの輝き フルフォード博士が語る自然治癒力』ロバート・C.フルフォード他/翔泳社 (1997)
『癒す心、治る力』アンドルー・ワイル/角川書店(1997)
『癒しの旅』ダン・ミルマン/徳間書店(1998)
『人生は廻る輪のように』エリザベス・キューブラー・ロス/角川書店(1998)
『音はなぜ癒すのか』ミッチェル・L.ゲイナー、菅原はるみ共訳/無名舎(2000)
『バイブレーショナル・メディスン』リチャード・ガーバー、真鍋太史郎 共訳/日本教文社(2000)
『奇跡のいぬ グレーシーが教えてくれた幸せ』ダン・ダイ、マーク・ベックロフ/講談社(2001)
『ライフ・レッスン』エリザベス・キューブラー・ロス、デーヴィッド・ケスラー/角川書店(2001)
『ヘルシーエイジング』アンドルー・ワイル/ 角川書店(2006)
『永遠の別れ』エリザベス・キューブラー・ロス、デーヴィッド・ケスラー/ 日本教文社 (2007)
『うつが消えるこころのレッスン』アンドルー・ワイル/角川書店(2012)
他多数。
© NPO法人日本ホリスティック医学協会 All Rights Reserved.
本サイト記事・画像の無断転載・無断使用を禁じます。